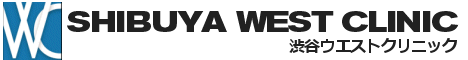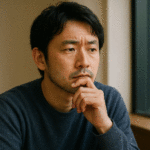ナトリウム摂取量の削減とカリウム摂取量の増加の重要性
ナトカリ比の考え方は、WHO(世界保健機関)をはじめとする国際的な保健機関や研究者が、高血圧や心血管疾患などの健康リスクを軽減するために提唱しています。この比率は、特に以下の分野で重要視されています。
WHOのガイドライン
WHOはナトカリ比に直接言及するというより、ナトリウム摂取量の削減とカリウム摂取量の増加の重要性をガイドラインで強調しています。以下の点が関連しています:
- ナトリウムの摂取基準
- 1日あたり2g以下のナトリウム(塩分では5g以下)を推奨。
- 高塩分摂取が高血圧や心血管疾患のリスク要因であることを指摘。
- カリウムの摂取基準
- 成人は1日あたり3.5g以上のカリウム摂取を推奨。
- カリウムはナトリウム排出を促進し、血圧を低下させる効果があるとされる。
- ナトリウムとカリウムのバランスの重要性
WHOは「ナトリウム摂取を減らし、カリウム摂取を増やすことが、高血圧予防および心血管疾患リスク低減に有効である」としています。これがナトカリ比の考え方の基礎となっています。
その他の研究と背景
- 研究論文
多くの疫学研究で、ナトリウムとカリウムの摂取比が高血圧や心血管疾患の発症リスクに与える影響が調査されています。たとえば、INTERSALT研究やPURE研究では、ナトリウム摂取量を減らし、カリウムを増やすことで血圧が低下することが示されています。 - 栄養学と公衆衛生の取り組み
米国の疾病予防管理センター(CDC)や日本の厚生労働省でも、ナトリウムとカリウムのバランスを考慮した食事指導を行っています。 - 伝統的な食生活との比較
伝統的な食生活では、加工食品の少ない自然食品(野菜、果物、豆類など)が豊富なため、カリウム摂取量が多く、ナトカリ比が自然に適正範囲になることが多いとされています。
ナトカリ比に基づく食事指導
現在、直接「ナトカリ比○○を目指すべき」という明確な数値目標はWHOや各国政府のガイドラインには示されていませんが、ナトリウム摂取量を控え、カリウム摂取量を増やす方針が一般的です。実際の比率は、摂取状況に応じて調整する必要があります。